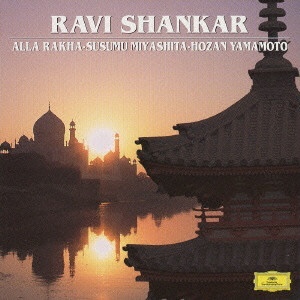『地球は民族の集まりなんだよ。あなたは地球市民でしょ、それではダメなんだ。』
現代邦楽・最後の巨匠、作曲家であり三十絃・箏演奏家である宮下伸。その至芸は、虚空において絃と爪から無限の色彩感を紡ぎ出す。空即是色、色即是空の境地を想起させる。
宮下は「音に入る」という表現をしばしば用いる。演奏中の宮下のマインドは、森羅万象において自然界が奏でる音、そのものとなって響きを創造するのである。
また特定非営利活動法人伝統芸術ライブラリー顧問であり、筆者の師匠でもある。

(宮下伸近影、令和二年1月 筆者撮影)
■父・宮下秀冽の軌跡
宮下伸の父でありやはり箏曲家であった宮下秀冽は、現在高崎市となっている倉渕村にある、造り酒屋に生まれた。旧倉渕村は、カルデラを構成し榛名湖を火口湖に持つ榛名山の西側に位置し、高崎市内からは榛名山を望ながら果樹園の広がる裾野をなだらかに登り、山あいを左方奥へ回り込んだところにある。倉渕は四季折々の表情豊かで、酒造りに適した銘水の湧く豊穣な土地である。
高崎市周辺の群馬県南部一帯は古墳等の遺跡も多く、また隣接する赤城山の麓には旧石器時代の磨製石器が出土した事で知られる岩宿遺跡がある。縄文文明が花開き、そして渡来文化が入り現代に至るまで、この大地は古代国家から現在の日本国家に属する「日本人」の生活の場となってきた。
特に大和朝廷成立以降はその統治政策において、高崎市の多胡碑(ユネスコ世界遺産)に示されるように帰化渡来人の移住も行われて、養蚕や窯業、鉱山開発などの産業技術の中心地ともなる。養蚕は後の官営富岡製糸場(同・世界遺産)の設置に繋がったと言えるだろう。
群馬県人は縄文文明に渡来人文化を重畳させ繁栄してきた古代日本人の血統を色濃く有している。
さて、宮下秀冽は高崎中学を出るが成人する前に失明し箏曲の道に入った。
宮下秀冽は斬新な作曲や演奏のスタイル、実力が宮城道雄に次ぐ箏曲家として認められていく。
■宮下伸の芸道
その父・秀冽に宮下伸は幼少から箏曲の手ほどきを受け、ピアノ等西洋音楽の素養も身に付ける。特にフルートはN響の奏者に師事するほどの英才教育ぶりであった。中学時代からのブラスバンドでは、あらゆる楽器を弾きこなした。
そして東京芸術大学へ進学する。在学中に安宅賞を受賞。芸大の後、NHK邦楽者育成会を首席で修了し、「NHK今年のホープ」に選ばれる。さらに伸は育成会の専科生としてさらに研鑽を積むこととなる。
芸大在学中の日本を代表する民族音楽の研究者であった小泉文夫の薫陶を受けた。
「箏はワールドミュージックである」と述べる宮下伸の音楽の捉え方・思想に強い影響与えたのも小泉であったと考えられる。
宮下伸の卓越した演奏や作曲の能力は具体的なプロジェクトや評価に結実していく。芸大を卒業してあまり間をおかずして第一回芸術選奨文部大臣新人賞受賞したのを皮きりに、「宮下伸 箏・三十弦リサイタル」の演奏、作曲により文部大臣より芸術祭大賞を受賞する。
また若い頃から政府の依頼や招待によって日本各地や世界各国で公演する。ヴァイオリニストのヴィーツラフ・フデチェック、シタールのラヴィ・シャンカル、フルートのジェームス・ゴールウェイらと次々に共演、それぞれビクター、ポリドール、イギリスRCAによってレコード化された。
作曲家として委嘱作品も多く、NHK委嘱「響の宴」の作曲では芸術祭賞文部大臣賞を受賞している。
(三十絃箏を演奏する宮下伸、筆者撮影)
また徹底的に磨き上げられた宮下伸の芸は、正確無比かつ技巧性に溢れ、その音色も表現が深い。
十三絃は勿論であるが、父秀冽の考案により創られた三十絃を自由自在に弾く能力は凄まじいの一言に尽きる。
三十絃は秀冽によって考案されてもほとんど使われず、ながらく宮下家に「吊して」あったものだったが、伸の類い希なる才能によって息を吹き込まれ、育て上げられたと言えるだろう。
十三絃が長さ一・八メートルに幅が三十センチ程度なのに対して、三十絃は長さ二・三メートルを超え幅が六十センチ強という、現用されるもので世界最大の箏である。
ビクターから収録時リミッターをカットして原盤にダイレクトカッティングすることによって、極限まで原音を追求したアルバム『三十弦』がリリースされている。津軽三味線の高橋裕次郎が競演するインプロビセーション(即興)によるセッションもあり、数百万円するというカッティング装置を何度も飛ばしたという、演奏者のみならずレコーディングスタッフも一発真剣勝負という、熱のこもったアルバムだった。
中東アジア地域に生まれたと言われる弦楽器。
弦楽器が到達した地において生まれた三十絃は、世界で最も進化した弦楽器だと言うことも出来るだろう。

(アルバム『三十弦』宮下伸、ビクター)
■越境する箏
ところで、先に述べたように宮下伸は著名な西洋音楽家とのセッションが多かった。そうしたな中、注目すべきなのは世界的なシタール奏者であるラビ・シャンカルとの出会いである。
ラビ・シャンカルは世界ツアーの中で世界各地のトップ・ミュージシャンとのセッションを重ねていた。ラビ・シャンカルは来日の折、日本の音楽家として箏の宮下伸、尺八の山本邦山(人間国宝・故人)と共に曲作りをしてアルバム『EAST GREETS EAST』を出している。
このアルバムは現在、アルバム『Vision of Peace: The Art of Ravi Shankar』に収録※されており、海外盤を入手することが可能である。(※『Vision of Peace: The Art of Ravi Shankar』Deutsche Grammophon , ASIN: B00005B4MW
Amazon Music Unlimitedでも聴取および購入・ダウンロード可:https://www.amazon.co.jp/dp/B00BH3UPNQ/ref=cm_sw_r_cp_awdb_c_f-npEbNV2X06K)
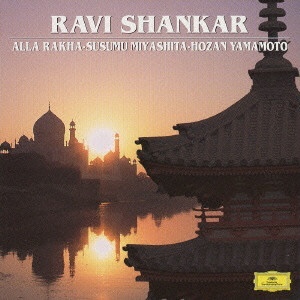
(『EAST GREETS EAST』ラビ・シャンカル、ユニバーサル)
一方、宮下伸の自身のアルバムとして他の民族楽器とセッションしているのが『THE ORIENT 民族の伝説』である。
〝国際的に活躍する箏の宮下伸が、父親譲りの三十絃箏を駆使して、アジア各地のヴィルトゥオーゾたちと競演した力作。在日のシタールのヘーゴダ、二胡の許可、カヤグム(ここでは杖鼓)の池成子、篠笛の藤舎名生とともに、アジアの民族詩を摘ぎ出している。〟(CDジャーナル データベース)
なお、シタール奏者のヘーゴダはラビ・シャンカルの弟子である。
弦楽器の最終到着地である日本音楽から、中国や韓国、そしてインドの民族楽器へとアプローチしているのが興味深い。
収録内容は以下の通りである。全て宮下伸による作曲作品。
1.「ムガール」シタール:プレームダース・ヘーゴダ
2.「長城」 二胡 :許可 、三十絃::宮下伸
3. 「悠久なる山河 」チャングム:池成子、三十絃::宮下伸
4.「正倉院 」笛:藤舎名生、三十絃::宮下伸
5.「素朴な風景」 三十絃独奏:宮下伸
※「THE ORIENT」を宮下伸YouTube公式チャンネルで公開しています。https://www.youtube.com/playlist?list=PLEVWJFK0l-OqcjI3ueDqAKU8Pg2K_4gDA
■そしてルーツの旅へ
歌人であり劇作家でもある寺山修司は、宮下伸の音についてこのように述べている。
〝宮下伸の三十弦の琴をはじめてきいたとき、私はその呪術的な力にがんじがらめにされてしまう自分を感じた。それは、音色で編まれた七色の蜘蛛の巣を思わせた〟
実際に宮下伸の生み出す音色に触れると、その奥行きの深さに驚きを禁じ得ない。玉鋼から緻密に造り込まれた刀の輝きの様に似ているかも知れない。
玉鋼の素材は日本の大地から産出されたものであり、それが縄文由来の精神と技術、そして渡来して融合した新たなる日本人と重畳した技術とで極限まで叩き磨き込んだのが日本刀であるとすれば、日本古来の伝統に由来し、現代人に至る精神により極限まで磨き込まれた至芸、それが宮下伸の芸道の達した境地である。
また宮下伸の音色、その響きは弦楽器が辿ってきた道のりを覚えている。
筆者が確信するのは弦楽器のルーツとは、現代日本人のひとつのルーツでもある、ということだ。
弦楽器は、アジアの西端から日の昇る方向を目指した人々と共に旅をして、やがて到着した日本列島の豊穣な自然に恵まれた文明に折り重なり育まれた。
その〝旅の成果〟である宮下伸の至芸と『THE ORIENT』の民族楽器とのセッションの織りなす響きは、筆者の魂を大きく揺さぶり、失われつつある旅路の記憶を求める「ルーツ」の旅へと、強く誘うのである。