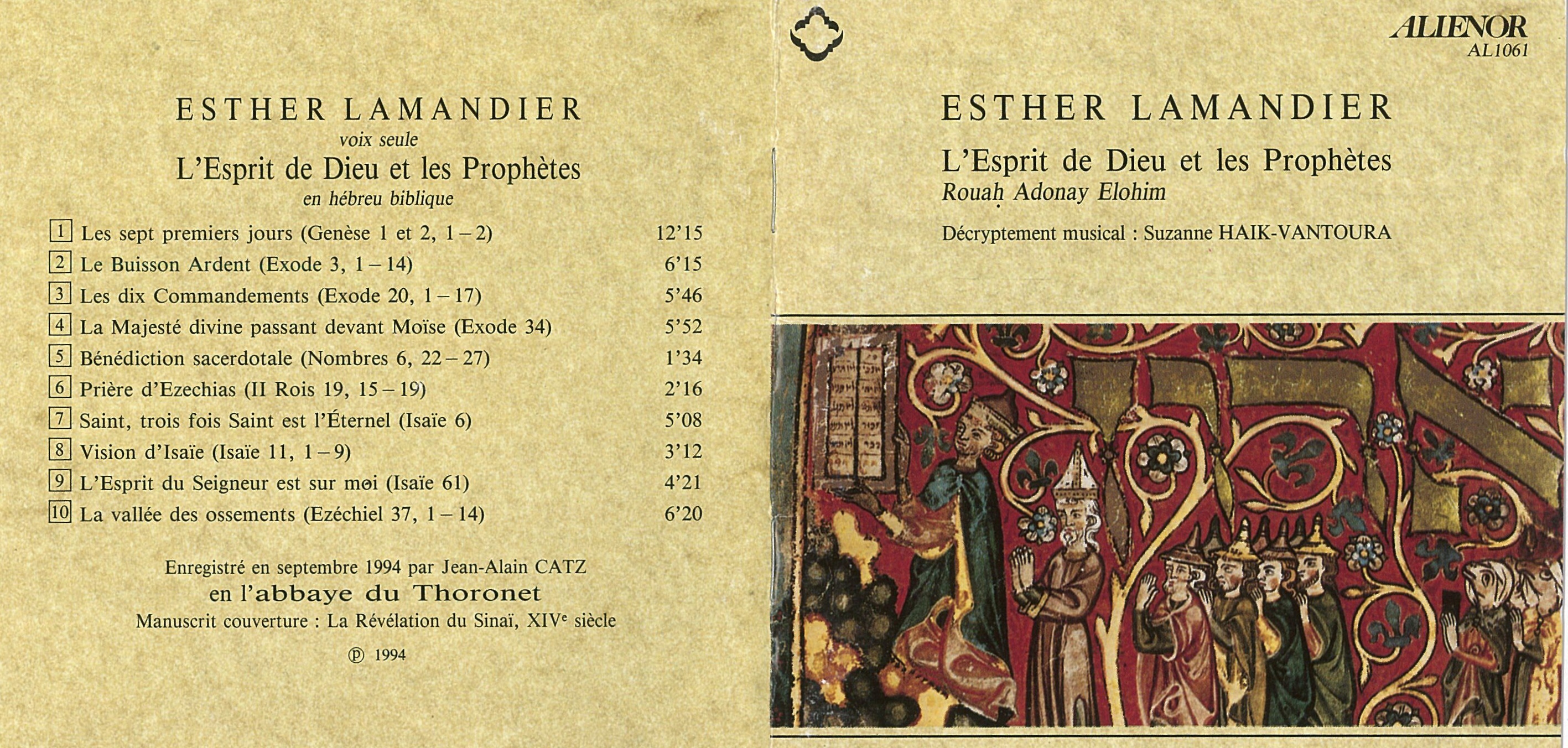平安京・大内裏の位置は、もともと現在の京都御所よりも西方にあった。
現在の京都御所の西方にある二条城が面するのは京都市街地を南北に貫く堀川通であるが、そのさらに西、今の千本通が丸太町通と交わるあたりに大内裏があった。
かつての大内裏のすぐ真北には小高くなった船岡山と呼ばれる丘があり、山頂の公園から眺めると両側に大文字・左大文字、南を向くと左斜め方向つまり南東に京都御所が、そして同じくらいに右斜め方向へ首を振ったあたりに広がる住宅密集地が、太秦の街である。
四条大宮のビジネスホテルに投宿して、嵐山行きの京福電車に乗り込んだのは平成19年の3月だった。
昼近く、2両編成のトラム(路面電車)は住民らしい人たちで賑わっている。
列車は西へ向かって出発する。街の裏通りのような面持ちの専用軌道を飛ばして走り、西院という停留所を過ぎると西大路通の信号を渡って三条通の併用軌道区間へ進入する。
ちなみに西院は〝さいいん〟と読む。が、隣接する阪急の駅名はそのままの読みなのだが、今乗っている京福電車の停留場名では西院と書いても読みは〝さい〟となる。
この不可思議な停留場のすぐ裏手には、京都時代にお世話になったお琴屋さんがあって、楽器の調整や道具・楽譜の購入、演奏会の楽器運びのバイトまでさせてもらったものだった。今は代替わりして屋号も変わり、お店も祇園の方へ移ったと聞く。
このお琴屋さんのバイトのおかげで、箏の沢井忠夫、尺八の山本邦山の、最晩年の演奏を舞台袖にて生で聴いた。筆者の師匠である箏・三十絃奏者の宮下神と、戦後邦楽最盛期の覇を競った男たちだ……筆者の師匠以外は既に故人である。
列車はアスファルトの上をゆっくり進む。
進路上の軌道敷にもお構いなしに割り込んでくるクルマを慎重にいなすように、列車は道路をゴロゴロと走り、路上に人の肩幅ほどの狭いホームがあるだけの山ノ内停留場に差し掛かる。
学生時代、雨の夜にバイクを走らせていてレールで滑り転倒したのはこのあたりだった。痛い思い出だ。
両脇に軒の連なる道路の真ん中を進行して再び専用軌道に入ったと思ったら、すぐにまた路面へ出て、列車は「蚕ノ社」に滑り込んだ。
停留場の敷地まで商店が占拠しているかのように見えるほど、密集した街だ。
この太秦は、平安京が出来る前から渡来人である秦氏が拓いていた街だ。平安京は造営大夫に任ぜられた和気清麻呂が造営に尽力したのだが、秦氏の協力により果たされたと言われている。
蚕の社、木嶋神社は「続日本紀」大宝元年(701年)の条に記載されていることから、平安京よりも前の、古くからの祭祀であることが明らかである。その名前の通り、秦氏がもたらした養蚕に縁がある。
蚕ノ社のホームを降りて少し歩くと、鳥居があった。

クルマや自転車が頻繁に行き交う住宅や商店の間を歩いていく。途中におばんざい屋さんがあったので、カボチャの煮付けなどの定食で腹ごしらえをした。中年の女性が一人で切り盛りしてるちょっと洒落た小さなお店だったが、関東とは味付けが違うもののダシが利いていて美味しかった。
京都というのは、住んでしまうと他の地方都市と変わることのない、庶民の街である。その中に歴史的建造物やエピソードが点在しているイメージなのだが、太秦はとりわけ庶民の色の濃い街だ。かつての大内裏からそれほど遠いわけではないものの、西大路より外側の所謂〝洛外〟にあったこと、また都色に染まらない独特の文化を持っていた、ということなのだろうか。
住宅街のど真ん中に森があり、そこが神社だった。